視野を広げる大切さに気づくきっかけとなったのは、社会人2年目に一緒に仕事をしていた、ある“視野の狭い先輩”との経験でした。
その人についてはプロフィール記事でも触れていますが、今回はもう少し踏み込んで、そのエピソードをご紹介します。
https://museum-hopper.com/profile/
1.「説教だ!」が口癖
その先輩の口癖は「説教だ!」。
怒鳴ることを“指導”だと信じているようなタイプでした。特に、私のような立場の弱い後輩には高圧的な態度で接し、逆に上司や他部署の人たちには驚くほど愛想がいい。まさに人によって態度を変える人の典型でした。
当時の私は、ただただその怒りを浴びないようにと、毎日気を張り詰めながら仕事をしていました。
2. 数字のミスで怒鳴られた日
ある日、私が提出した報告書に転記ミスがありました。気づいた時点で即座に修正しましたが、先輩は目を吊り上げて、
「社会人失格だ! 説教だ!」
と机を叩きながら怒鳴りました。それは指導ではなく、ただ感情をぶつけているだけのように感じました。ミスの原因や改善案を一緒に考える姿勢など一切なく、「怒り=指導」と思っているようでした。
ところが数週間後、先輩がまったく同じような転記ミスをした場面に立ち会いました。私は「どうするのだろう」と見守っていましたが、先輩は「すぐ直しといて」と苦笑いで済ませていました。謝罪も反省もなし。その瞬間、「ああ、この人は自分の感情をぶつけていただけだったのだ」と、はっきり感じました。
3. 原因を調べずにすぐ怒鳴る
別の日、システムトラブルが発生した際も、先輩は詳細を確認することなく、
「お前が変な設定をしたせいだろ!」
と怒鳴ってきました。私は設定をいじった記憶がなかったため、調査を進めたところ、原因は先輩自身が前日に仕込んだバッチ処理にあることが判明しました。
それを報告すると、「まあ、次から気をつけろよ」と曖昧に済まされました。こちらには何度も怒鳴っていたのに、自分のミスには謝罪すらない。こうしたダブルスタンダードに、強い不信感を抱いたのを覚えています。
4. “言った・言わない”で評価を下げられる
特に理不尽だったのが、「〇〇をやっておいて」と先輩が口頭で言った“つもり”だった指示に関する出来事です。私はその指示を受けた記憶がなく、紙にもメールにも記録は残っていませんでした。先輩が言った気になっていたのか、私が聞き漏らしていたのかはわかりません。
本来、こうした伝達ミスは職場で起こり得るものです。しかし先輩は、「言ったのにやらなかった」と決めつけ、その年の私の評価を下げる材料にしました。記録も裏付けもないまま、他人の評価を自分の感情だけで決める姿勢に、私は言葉を失いました。
5. 心理的安全性のない職場
こうした経験が積み重なるうちに、私は報告や相談をためらうようになっていきました。「また怒鳴られるのでは」と思うと、伝えるべきか迷ったことも、つい黙ってしまう。すると後から「聞いてない!」と怒鳴られる――そんな悪循環が日常になっていました。
この状況は、まさに「心理的安全性」が欠如した職場だったと思います。安心して発言できない環境では、チームは機能しません。そして、誰かが常に不安を抱えながら働いている時点で、それは職場ではなく、ただの“作業場”だと感じるようになりました。
反面教師からの学び
いま思い返しても、その先輩のことは大嫌いです。ただ、「ああはなりたくない」という強い指針をくれたという意味では、紛れもなく反面教師でした。
この経験から私が学んだ仕事で大切にしていることは、以下の3つです。
- 指示や重要な伝達は、必ず記録に残す(メールやチャット)
- ミスを怒りで処理せず、事実と改善策に目を向ける
- 立場によって態度を変えないことを意識する
おわりに
怒鳴り声が響いていたあの職場の風景は、もう遠い過去です。けれど、あのときの経験は今の私の働き方の土台になっています。
怒られたこと、悔しかったこと、不条理だったこと——そのすべてが、いまでは私にとっての学びです。
視野の狭い先輩との出会いは、私の視野を広げてくれる機会でもありました。こうして振り返ると、あの先輩は私の人生における**“最強の反面教師”**でした。
あのときの不快な経験の数々も、振り返れば「自分の軸をつくる材料」になっています。
そう思える存在に、社会人2年目で出会えたこと。それ自体が、私にとって大きな意味を持つ出来事でした。
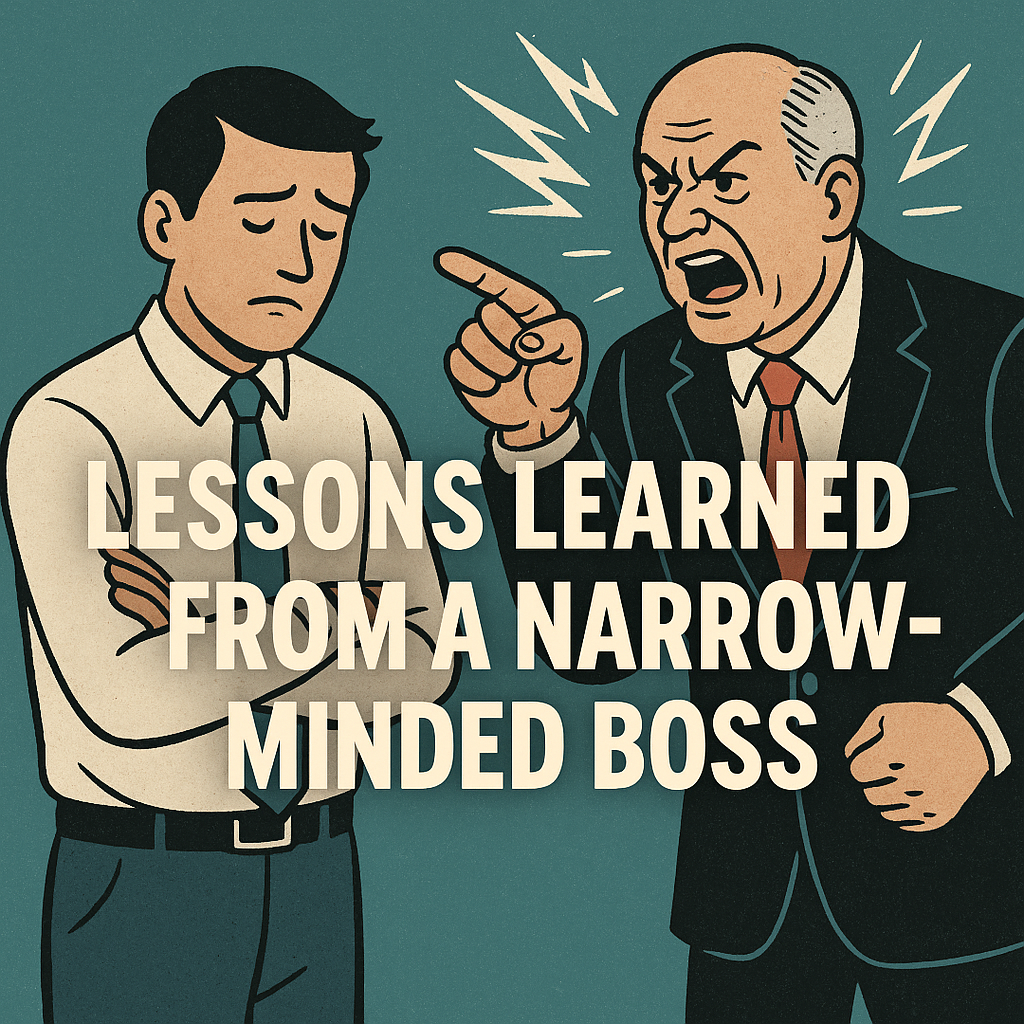
コメント