社会や働き方が大きく変わりつつある今、自分の人生をどのように設計していくべきか――。
そのヒントが詰まった一冊が、山口周さんの『人生の経営戦略――自分の人生を自分で考えて生きるための戦略コンセプト20』でした。
企業の戦略理論をベースにしながら、個人の人生にも応用できるフレームを20個紹介しており、どの言葉も深く考えさせられるものでした。
本記事では、私が特に心に残った3つのコンセプトを紹介しつつ、自分の経験や考えと結びつけてご紹介します。
「短期の合理」より「長期の合理」が大事
「優れた戦略とは、長期的・全体的には合理的だが、短期的には不合理に見えるものだ」という考え方です。
これは、私自身が日々考えていることと一致しました。
たとえば私は、会社での1〜2年の評価にはそれほど価値を感じていません。むしろ、短期的な成果に縛られず、自分の選択肢を広げたり、視野を広げたりすることにエネルギーを使いたいと考えています。
たとえば副業や投資、読書や旅。これらは今すぐ評価されるものではないかもしれませんが、10年後の自分を豊かにしてくれると信じている「長期の合理」です。
過去の成功者たちも、当時は理解されず不合理に見えた選択をしていたという話に触れ、「今、周りにとって不合理でも、自分にとっての戦略なら貫いていい」と背中を押された気がしました。
AI時代にこそ必要な「リベラルアーツ」の力
「問いを立てる力」がますます重要になっていく。これも本書の中で特に印象に残ったメッセージのひとつです。AIがどれだけ優れていても、それは「正解を提供する」能力に過ぎません。
しかし、そもそも「どんな問いを立てるか」、「どんな価値を追求すべきか」を考える力は、依然として人間に委ねられています。
著者は、それを養う手段として「リベラルアーツ=教養」が不可欠だと述べています。この考え方は、私の趣味である美術館や博物館巡りとも重なりました。芸術や歴史に触れる中で、時代や価値観の移ろいを感じたり、自分とは違う視点に出会ったりする――それはまさに「自由に思考する技術」を鍛える時間だと思います。
リベラルアーツとは、単に知識の蓄積ではなく、「人間らしい問い」を立てる土台なのだと感じました。
「自分のモノサシ」で生きるということ
「他人のモノサシで生きていないか?」という問いも、非常に鋭く刺さりました。
会社の評価、上司の価値観、周囲の空気といった、自分の軸ではなく、“誰かにとっての正解”に合わせて生きてしまっていることがあります。でも本書でははっきりと、「他人のモノサシを受け入れることは、そのまま支配を受け入れることになる」と断じています。
私自身も、仕事や人生の判断を下すとき、「自分が納得しているか?」という基準を大事にしたいと思っています。たとえ周りから見て“非常識”に映っても、「自分はこうありたい」という感覚を大切にしていきたい。それこそが、人生を主体的に生きるための戦略なのだと改めて気づかされました。
人生という企業の「経営戦略」を考えるきっかけに
『人生の経営戦略』は、どのステージの人にも気づきを与えてくれる一冊です。私自身、人生の節目ごとに何度でも読み直したいと思いました。
- 長期で物事を捉える視点
- リベラルアーツを通じて思考力を磨く姿勢
- 他人に流されず「自分のモノサシ」で生きる覚悟
どれも、すぐに答えは出ないけれど、これからの人生で何度も立ち返る価値がある考え方です。
人生の方向性に迷っている方、自分らしい働き方を模索している方には、ぜひ手に取っていただきたい一冊です。
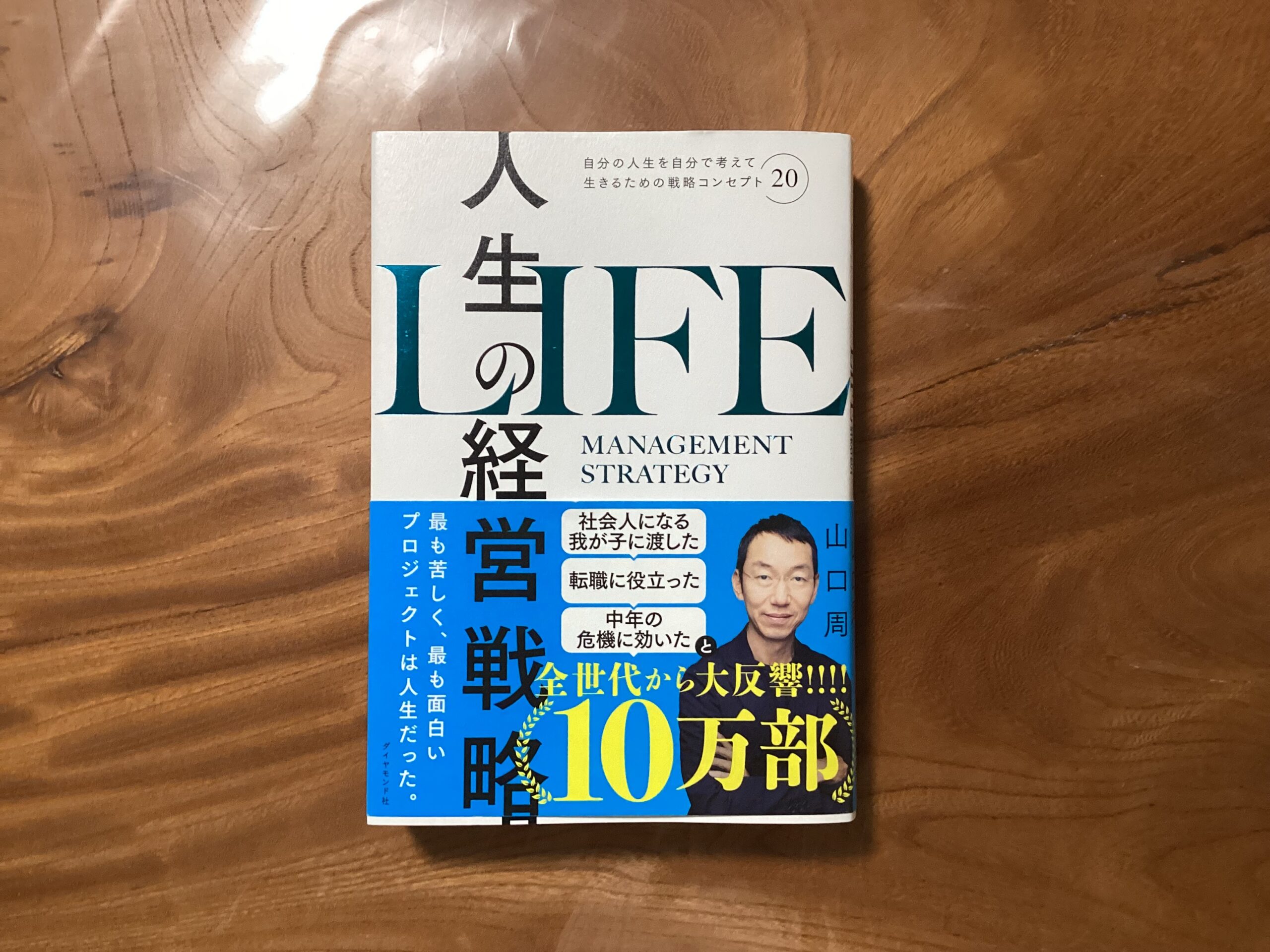
コメント